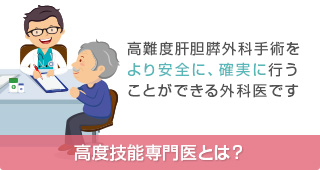胆管がんとは
胆管がんの概要
まず、胆道とは胆汁の通り道である胆管、胆のう、十二指腸乳頭部の総称で、これらの部位に発生する悪性腫瘍を胆道がんと呼びます。肝臓で作られた胆汁は肝内の胆管(肝内胆管)から上部胆管(肝門部領域胆管、近位胆管)を通って、いったん胆のうで蓄えられて凝縮され、細い胆のう管から下部胆管(遠位胆管)、乳頭部を通って十二指腸に流れ込み消化を助けます。胆汁は肝臓で生成される黄褐色の消化液で脂肪の分解と吸収に重要な役割を果たします。胆道がんはがんの発生部位別に肝内胆管がん、胆管がん(肝門部領域胆管がんと遠位胆管がん)、胆のうがん、乳頭部がん(十二指腸乳頭部がん)に分けられます。
【図1】胆管とその周囲の臓器

胆道がんは日本では決して珍しいがんではなく、年間2万人以上が新たに診断されています。男性では9番目、女性では7番目に多いがんです。また、50歳代から増え始めて70歳代、80歳代の高齢者に多く、胆管がんと乳頭部がんは男性、胆のうがんは女性に多い傾向がみられます。なお、最近では印刷業務で使用されているジクロロメタン、ジクロロプロパンを長期間使用することで胆管がんの発生が増加することも報告されています。ここでは胆管がんに注目してその概要を述べていきます。
胆管がんの症状
胆管がんの最初の症状として黄疸(おうだん)が挙げられます。皮膚や目の白い部分が黄色くなる症状です。これは胆管にがんができると、胆汁が流れにくくなり、これにより胆汁が血液中に逆流していきます。そうすると血液中の胆汁成分であるビリルビン濃度が高くなり黄疸が発生します。これを閉塞性黄疸といいます。胆汁の流れが高度に障害されると腸内に胆汁が流れなくなり、便の色が白っぽいクリーム色を呈するようになります(白色便:はくしょくべん)、また尿中の胆汁成分が多くなると尿が茶色っぽく、濃くなります(褐色尿:かっしょくにょう)。その他、腹痛、発熱、全身倦怠感、食欲不振、体重減少なども伴う可能性があります。
胆管がんの診断
上記の症状を認めた場合は胆道がんを疑い、図2に示す流れで詳しい検査を進めていきます。
【図2】胆管がんの診断の進め方

まず胆道がんを疑った場合には血液検査と超音波検査を施行します。胆道がんにより胆汁の流れが悪くなると血液中のビリルビン、アルカリフォスファターゼ(ALP)、γ-GTPなどの数値が上昇します。診断の補助的な役割をする腫瘍マーカーとしてCA19-9、CEAも測定します。腹部超音波検査は外来で比較的簡単に検査ができます。肝臓、胆のう、胆管に異常があるか、胆汁の閉塞が疑われるかなどを評価します。
これらの検査で胆管がんが疑われた場合には続いてMDCT(マルチスライスCT)検査を行います。いわゆるCTスキャンですが、最近の機器の進歩により1回の撮影で様々な角度からの画像を作成することが可能です。静脈より造影剤を注入することにより、画像をより鮮明にしてがん病巣の場所、広がり、血管(主に門脈、肝動脈)の位置関係、浸潤の有無を評価可能です。
MDCTにより胆管がんの診断がより明確になったのちに、超音波内視鏡検査(EUS)、MRIあるいはMRCP、PET検査などを行います。超音波内視鏡検査(EUS)とは内視鏡の先端に超音波装置がついていて、体外超音波と比較し、より詳細な情報を得ることが可能です。MRIはX線ではなく強力な磁石を使用した検査になりますが、MRCPとは、その画像解析により胆管、膵管像まで評価することが可能です。最近ではPET検査も行われることが多いですが、これは特殊な放射線元素を注入し、全身におけるがんの広がりを確認することができます。
以上の検査結果より画像上、胆管がんと診断された場合、次の処置・検査に進みます。胆管がんの患者さんは通常黄疸をきたしていることが多いので黄疸を改善させる処置(減黄術:げんおうじゅつ)が必要になります。減黄術には内視鏡的と経皮的ルートの2つがあります。内視鏡処置は十二指腸乳頭より内視鏡的逆行性胆管造影(ERC)を行い、引き続き、狭い部分を通過してチューブを留置し、そのチューブより胆汁を体外に誘導します。経皮的処置は超音波を施行し、その画像をガイドに肝臓の中の胆管を穿刺しチューブを留置します。これらの処置と同時に病理検査(細胞診、組織診)を行うことが可能です。この処置・検査により胆管がんの確定診断が得られます。
胆管がんの進行度 病期(ステージ)
全てのがんに進行度を表す表現として病期(ステージ)を用います。日本の各学会が定めた「癌取扱い規約」による病期分類とUICCという国際分類があります。いずれも局所の進行度合い、リンパ節への転移状況、遠隔転移(肺、肝など)の有無などから決定し、これにより治療方針が決定します。
胆管がんでも肝門部領域胆管がん(図3A)と遠位胆管がん(図3B)ではその病期決定は多少異なります。
【図3】
A: 肝門部領域胆管がんの病期分類

B: 遠位胆管がんの病期分類

病期を要約しますと、0期は上皮内、すなわち胆管の表面に留まるがんです。1期は概ね胆管壁に留まるがん、2期は胆管壁を越えるがんとなります。局所進展で合併切除が可能な臓器、血管に浸潤があると肝門部領域胆管がんの場合は3A期、遠位胆管がんでは2A期となり、リンパ節転移があると肝門部領域胆管がんでは3B期、遠位胆管がんでは2B期となります。遠隔転移がある場合はいずれも4期となります。
胆管がんの治療
臨床病期により治療方針が異なります。大まかな治療方針を図4に示します。
【図4】 臨床病期別の治療方針の流れ

胆管がんに対する手術療法
臨床病期において切除可能病変であれば、手術が最も治癒が期待できる治療方法です。胆管がんでは決まった手術術式といったものがなく、がんの場所、広がりに応じた術式が選択されます。一般的には肝門部領域胆管がんの場合は肝切除、胆管切除を伴う術式が選択され、遠位胆管がんの場合は膵頭十二指腸切除術が選択されます。図5にその例として、肝門部領域胆管がんに対する肝右葉切除、肝外胆管切除(図5A)と遠位胆管がんに対する膵頭十二指腸切除術(図5B)の切除範囲を示します。
【図5】胆管がんの一般的な切除範囲
A.肝門部領域胆管がんに対する肝右葉切除、肝外胆管切除術

B.遠位胆管がんに対する膵頭十二指腸切除術

特に肝門部領域胆管がんでは近傍の門脈、動脈に容易に浸潤を来します。胆管がんの進展範囲により肝左葉あるいは右葉切除が選択されます。病変が局所に伴っている場合、あるいは肝機能が十分でない患者さんには肝臓の中央から下の区域だけを取る場合もあります。また、肝臓全体の60%以上を切除するような肝切除術を予定する場合は、術後の肝不全が心配になりますので、術前に切除側の門脈血流を止める処置(門脈塞栓術)が行われる場合もあります。いずれの術式も周囲のリンパ節とともにがんの進展部位を全て切除する根治術が長期生存を得るには必須の治療法です。
術後の合併症として、肝門部領域胆管がんでは肝葉切除、肝外胆管切除後の肝不全と胆管と小腸(空腸)の縫合不全(うまくつかず、胆汁が漏れてしまう合併症)が挙げられ、遠位胆管がんでは膵頭十二指腸切除後の膵液瘻(膵臓と消化管の吻合がうまくつかず膵液が漏れてしまう合併症)が挙げられます。胆汁、膵液がお腹の中に漏れてしまうとそこに膿の塊(膿瘍)を形成し、高熱の原因となります。また、この膿瘍が血管、主に動脈に接していると血管の壁が徐々に弱くなり、“こぶ”を形成することがあり(仮性動脈瘤)、これが大量出血の原因となり緊急処置が必要な場合があります。
胆管がんに対する化学療法(抗がん剤治療)
胆管がんに対する化学療法として、ゲムシタビンとシスプラチンを併用する化学療法が標準治療として確立しています。切除が困難な胆管がんの患者さんに広く行われている治療です。多くは外来で週1回3時間程度かけて点滴し、2週にわたり連続投与し、3週目は休薬します。このような3週間を1コースとして治療を繰り返します。上記2剤の化学療法以外にはテガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム(S-1)で治療する場合もあります。どの薬剤を使用するのかに関しては、患者さんの全身状態や症状によって検討します。
胆管がんに対する放射線治療
手術が不可能で遠隔転移のない場合、がんの進行抑制を目的として放射線治療を行う場合がありますが、有効性については十分な検討がなされておらず標準治療ではありません。疼痛を緩和するために行うことがあります。
胆管がんに対する免疫療法
患者さんの中には標準治療の手術や薬物治療ではなく、免疫療法を選択する人がいます。しかし、胆道がんに関しては、免疫療法が有効との証拠は一切ありません。また、免疫療法の副作用で薬物療法が受けられなくなる場合もあります。まずは現段階では最も有効な治療である標準治療を受けてください。